命を守る合言葉⁉ その名は「いかのおすし」

うちの家にある子供とのルールを一つ紹介します。
それは「学校から帰ってきたら、プリントとテストはリビングのテーブルに出すこと」。
なぜそんな決まりができたのかというと…ある日、ランドセルの奥底から「しわっしわ&インクにじみまくり」の保護者向けプリントが無残な姿で発見されたから(笑)
以来、「テーブルに置く!」が我が家の鉄の掟になりました。
今日はそんな鉄の掟通りにおかれたプリントのお話です。
自分の命を守るために
テーブルの上にピラっと置かれたプリントには、小学校から配られたものとは思えないくらい重いタイトル。
ひらがなを多用されていることからも、小学生向けの警察署からの注意喚起のプリントのようだった。
自分が小学生だった30年以上前には、「自分の命を守る」なんて発想は小学生にはなかったように思う。
それくらい今が物騒な世の中になったってことなんだろうなぁ…なんて考えると悲しくなる。
プリントを読み進めていく。
「い か の お す し」
これが、自分の命を守る合言葉であるらしかった。
いかのおすしの「いか」
「ついていかない」の「いか」
さっそく突っ込んでもいいですか?
「い」と「か」で別れると思ったら、まさかの「いか」かい!
何かの頭文字になっているのかと思いきや、まさかの「ついていかない」の「いか」ですか。
さすが警察の方です、考えに柔軟性は必要ですね。
えーーと…話を戻します。
知らない人や知っている人にもついてはいかない。お菓子やゲームをあげると言われても断ろうとあります。
確かに大事なことですね。「知っている人にも」というところ、最近のニュースを見ていると頷けてしまいますよね。
いかのおすしの「の」
「のらない」の「の」
知らない人や、知っている人の車に乗らない。
逃げるときは、車の進む方向とは逆の方向に逃げよう。
ここでも「知らない人や知っている人」のフレーズ…。
よっぽど知り合いからの犯罪が多いのかなぁ。
そして、逃げるときは、車の進行方向とは逆へって、いきなり具体的なアドバイス。
でもこれも大事なこと。
いかのおすしの「お」
「大声を出す」の「お」
これは何となく予想できた、大声を出すということ。
大きな声を出す。「たすけて」と大きな声で叫ぼう。
でも驚いた時や怖い時って、なかなか大声って出せないものです。
ランドセルを背負っている通学時には、防犯ブザーがついているから子供には防犯ブザーを鳴らしながら走ってお店とかがあったら、お店の人に助けを求めるようにわが家では伝えてあります。
いかのおすしの「す」
「すぐ逃げる」の「す」
こわい、あぶないと思ったら、すぐ逃げる。大人に人のたくさんいる所へ逃げよう。
「大きな声を出す」ことと、「すぐ逃げる」はワンセットだなぁと感じています。
日頃から何が怖いのか、危ないのかを親子で話し合うのも大切だと思います。
いかのおすしの「し」
「大人の人に知らせる」の「し」
大人の人に知らせる。何があったのか、近くにいる大人に話そう。相手の特徴も覚えて伝えましょう。
子供ってなかなか怖い思いをしても、大人や親に言えないことも多いそうです。
特に学年が上がるにしたがって、恐怖や混乱、罪悪感や恥ずかしさ、心配をかけたと怒られてしまうなど様々な言えなくなってしまう要因があるようです。
日頃から、子供の気持ちに寄り添い、何でも話せる安心できる環境づくりが大切ですね。
まとめ
実際に子供が通っている小学校の学区内でも、度々不審者情報の一斉メールが届いたりします。
日頃から子供と「もしも」の話をするのもいい方法かもしれません。
僕が住んでいる地域の警察だけの合言葉なのかもしれませんが、小学生のお子さんがいらっしゃる方はぜひお子さんに
「命を守る合言葉「いかのおすし」って知ってる??」
って聞いてみてください。
「なにそれ、知らないっ!」って返答からでもぜひお子さんとの「もしも」の時の話をしてみてください。
自分が育った時代よりも、物騒な世の中になってしまったからこそ親と子供の会話は大切です。
最後に…
お客さん、ご注文は? へいっ、いかのおすし一丁っ!
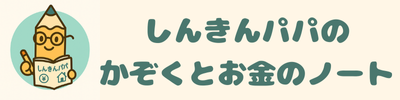

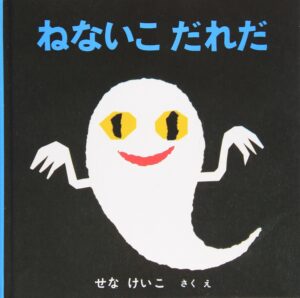
コメント