【弁護士から通知書】退職勧奨で「夫は介入するな」と言われた話|これは違法?実体験で解説
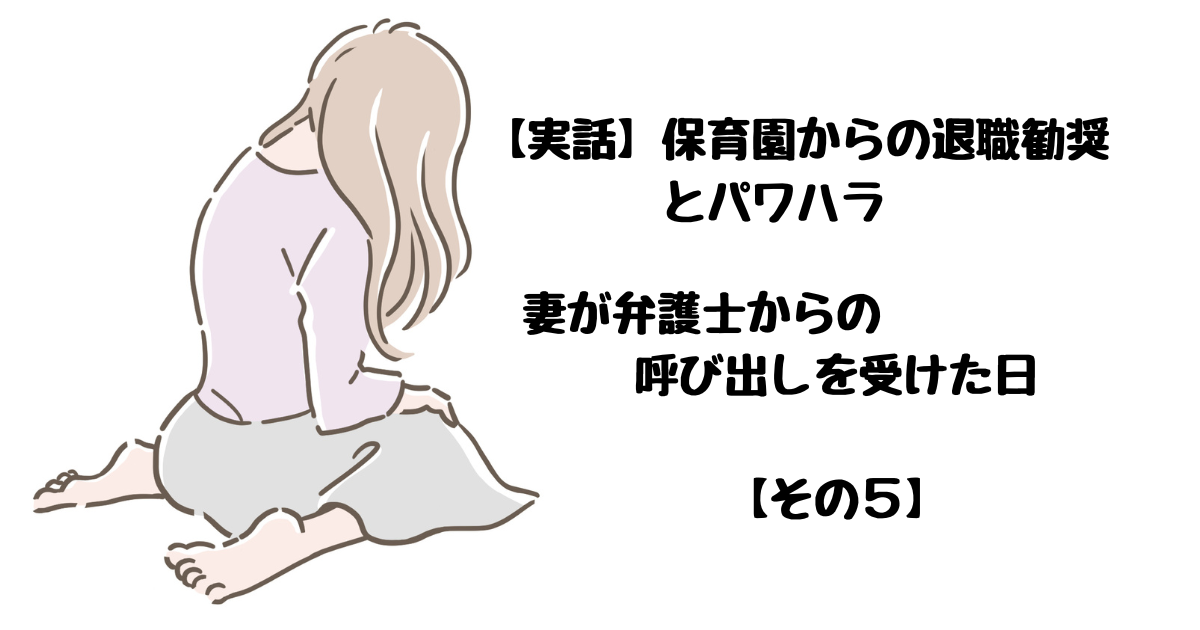
この記事でわかること
- 弁護士から「通知書」が届いた場合の正体と意味
- 退職勧奨で家族(夫)が関与するのは違法なのか
- 弁護士面談は拒否できるのか
- 精神的に追い込まれたとき、何を優先すべきか
これは、僕の妻に本当に起きた話です
そして今もなお、進行中の出来事です。
この先どうなるか、僕たち自身にもまだわかりません。
前回の記事では、園長との面談後に行われた幹部会議で語られた、信じがたい暴言の数々についてお伝えしました。
今回はその 10日後 に起きた、
- 弁護士からの呼び出し
- 夫である僕宛に届いた「通知書」
この2つについて、事実ベースで書いていきます。
副園長から突然告げられた「弁護士との面談要請」
園長との面談後も、妻は出勤を続けていました。
悔しかったからです。ここで辞めたら、すべて園長の思い通りになる。
けれど、心身が限界に近づいているのは明らかでした。
出勤前、涙を流しながら準備する妻に、子どもが言いました。
「ママ、もう頑張らなくていいよ」
それでも妻は踏ん張っていました。
そんなある日、副園長から突然こう告げられます。
「〇日の▲時、弁護士との面談をお願いしたいのですが」
弁護士との面談。しかも一対一。
この時点で、妻は強い恐怖を感じたと言います。
退職勧奨で「弁護士面談」は拒否できるのか?
結論から言うと、
▶ 弁護士との直接面談に“応じる義務はありません”。
会社側は「話し合い」と言いますが、
実態は 心理的圧力をかけて退職に誘導する場 であることが少なくありません。
特に、
- 法律知識のない個人
- 精神的に追い込まれている状態
この2つが揃うと、極めて不利です。
夫宛に届いた「弁護士からの通知書」
その日、偶然にも僕のもとに一通の書面が届きました。
差出人は——
妻の勤務先の 顧問弁護士。
中身は「通知書」。
要約すると、こう書かれていました。
「あなた(夫)は当事者ではないので、介入しないでください」
正直、強い違和感を覚えました。
なぜなら、最初の退職勧奨時、園長自身がこう言っていたからです。
「ご主人と相談して決めてください」
それなのに今さら
「口を出すな」「関与するな」。
あまりにも筋が通っていません。
退職勧奨に「家族が関与」するのは違法なのか?
結論をはっきり言います。
▶ 違法ではありません。
配偶者が精神的に支えること、
代理的に助言・同行・相談することは、ごく自然な行為です。
むしろ、
- 精神的負荷が強い状況
- パワハラ・不当な退職勧奨が疑われる状況
では、家族の関与は合理的と評価されることもあります。
見えてきた保育園側の狙い
この一連の流れで、僕たちにははっきり見えました。
狙いはこれです。
- 夫を排除する
- 妻を一人にする
- 弁護士という「権威」で圧をかける
- 退職に追い込む
通知書は、法的手続きというより心理的威圧でした。
弁護士から通知書が届いたとき、取るべき対応
僕たちが取った行動は、次の2つです。
① 弁護士との直接面談を拒否
話すなら、書面のみ。
② すべてのやり取りを記録
日時・発言・通知内容を整理しました。
これは結果的に、自分たちを守る行動になりました。
限界を迎えた妻と心療内科の診断
それでも、精神的な負荷は続きました。
- 不眠
- 動悸
- 吐き気
僕は心療内科の受診を勧めました。
診断結果は、
- 急性ストレス反応
- 抑うつ状態
医師からは、**「休養が必要」**と告げられました。
退職勧奨・パワハラに悩む人へ伝えたいこと
声を大にして言いたい。
- 弁護士という言葉に怯えなくていい
- 通知書が来ても、あなたが悪いとは限らない
- 一人で抱え込まないでいい
守られるべきなのは、会社ではなく「人」です。
次回予告|退職勧奨を受けたとき「本当にやるべき行動」
次回は、
「パワハラ・不当な退職勧奨に遭ったとき、実際に取った具体的行動」
- 行政への相談先
- 記録の残し方
- やってはいけないNG対応
を、実体験ベースでまとめます。
※本記事は、特定の個人・施設を誹謗中傷する目的ではなく、
実体験をもとに「同じように悩む人が声を上げるきっかけ」を
共有するために記録しています。
-
URLをコピーしました!
-
URLをコピーしました!
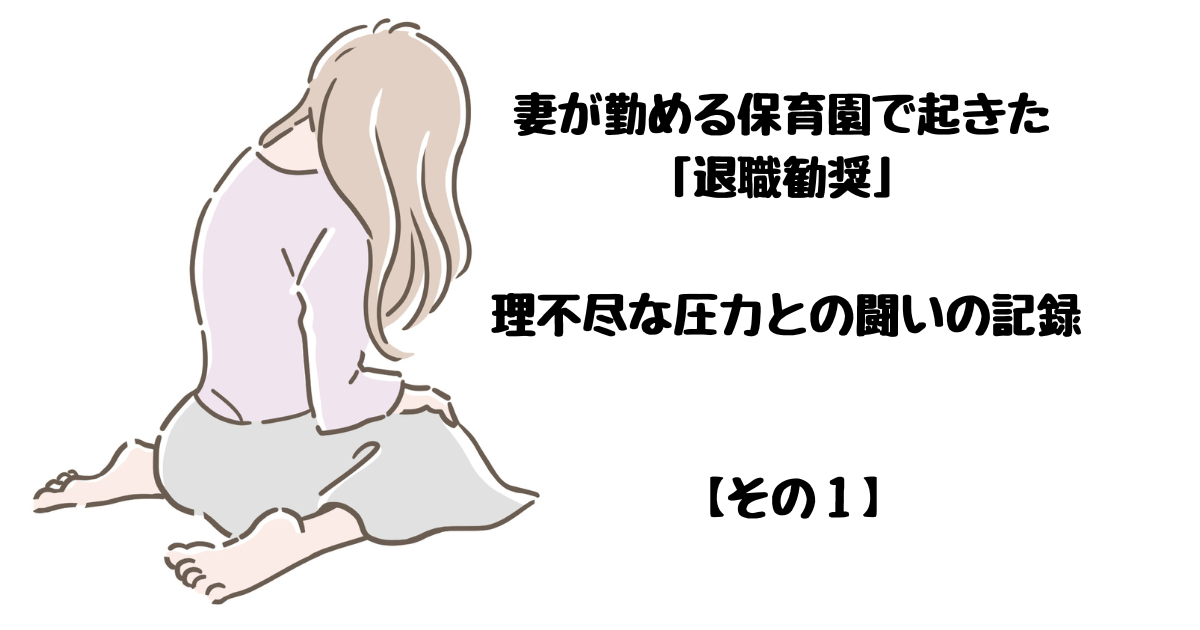
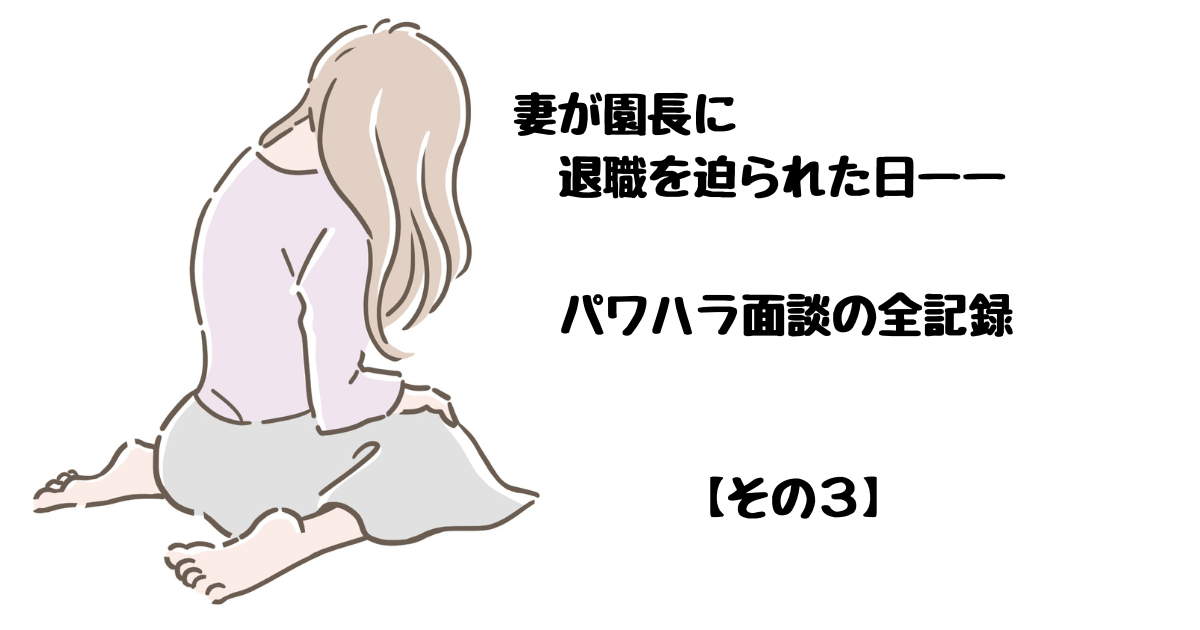
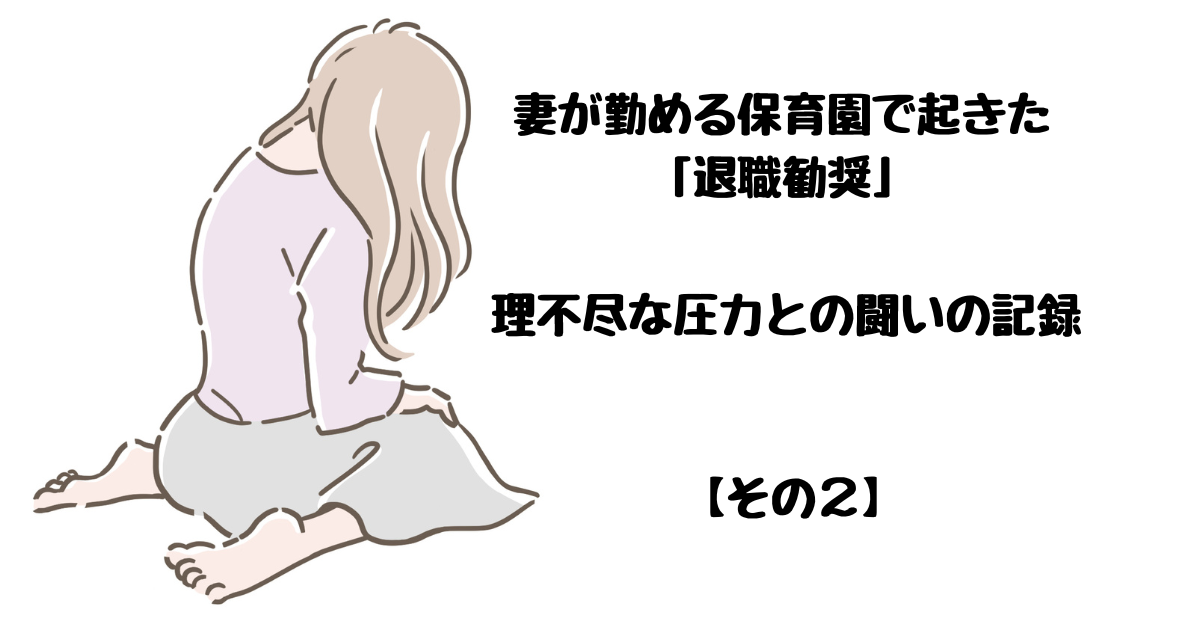
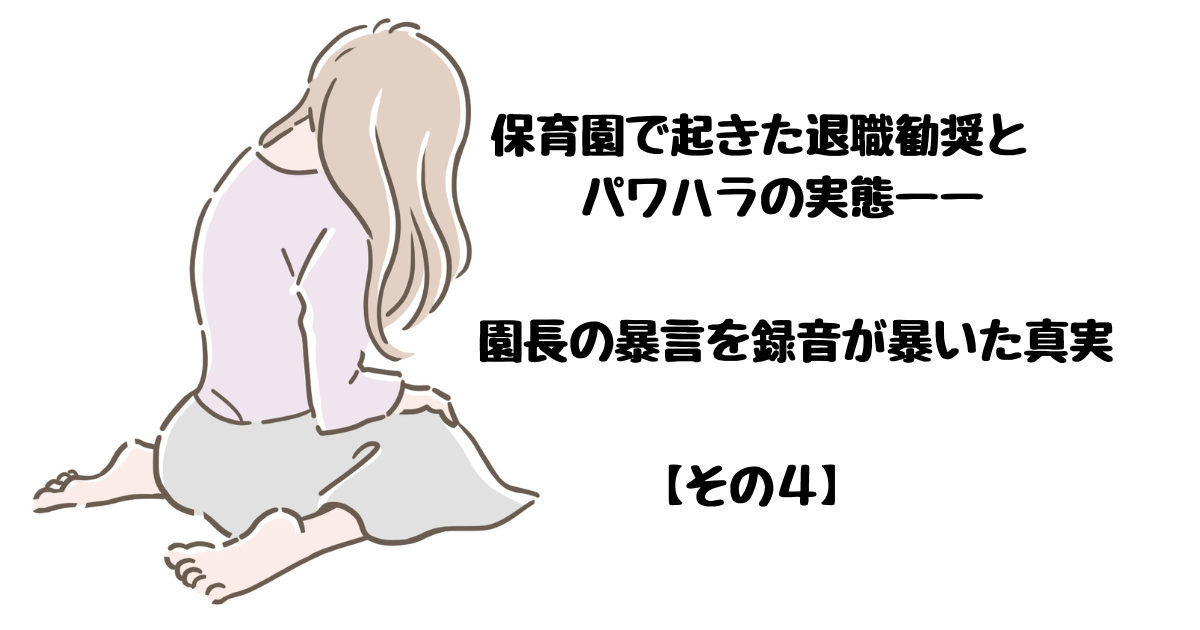
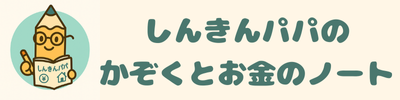
コメント